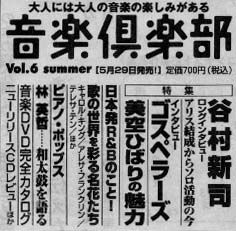特集:「音楽倶楽部」ゲットまでの長い道のり、
略して「オヤジぃ。の一番長い日」(笑)その1 |
|
おまえさんから、熱烈な投稿文をいただきました。どうやら、血液中のチンペイさん濃度がかなり高い方のようです(笑)。
おまえさんの熱い思いが直に伝わってくるようで、私もうれしい限りです。 |
|
こんにちは。私はチンペイさんのファンで、ハンドルネームは「おまえ」と言います。もちろん、アリスのあのヒット曲からとっているということは一目瞭然ですよね。でも、突然「キャハハハ!」なんて笑い出さないのでご安心を(笑)。
こんな文章を書いたのは、私が「音楽倶楽部」という雑誌にチンペイさんのロングインタビューが掲載されていることを知ってから、その雑誌をゲットするまでの長い長い道のりをみなさんに知ってもらいたかったからです。まあ、知ってもらったからといってどうということはないのですが、もう少し私に語らせてください。 |
|
|
(1)発見(笑)から取り寄せ注文までの長い一日
事の発端は、2001年5月28日の読○新聞です。何気なく一面の下に掲載されている本や雑誌の広告を見ていたとき、この一文が目に飛び込んできました。そこへ目がいくであろう事は、当然予想されていたのかもしれません。そこには、
「大人には大人の音楽の楽しみ方がある─音楽倶楽部」
「特集─谷村新司 ロングインタビュー アリス結成からソロ活動の今」
と書かれていました。ファンである私は飛び上がりそうなほど喜んだ、ということはもちろん言うまでもありません。発売元は、ヤマハミュージックメディア。あまり聞いたことのない雑誌だな、と何気なく思ったのですが、それからすぐに、私は当然のことのように「ダダダ ダ〜ラ〜」(←「おまえ」をイメージしてくださいね)と本屋へと足を運んだのでした。
まずは地元ではある程度大きい○○堂書店へ。音楽雑誌を置いているコーナーをくまなくさがしましたが、「音楽倶楽部」の「お」の字も見つかりませんでした。おそらく売り切れてしまったのだろう、と思い店員さんに「音楽倶楽部」という雑誌を探しているのですが……と尋ねたところ、店員さんは丁寧に在庫があるかどうか確認してくれましたが、その結果は「うちでは取り扱っていません」でした。無惨です。しかし、その店員さんは「紀○○屋書店だったらうちと問屋が違うので扱っているかもしれませんね」、と言ってくれました。その足で紀○○屋書店へ。そこでも音楽雑誌のコーナーをくまなく探しましたが、お目当ての雑誌は見つからず。仕方なく店員さんに、「音楽倶楽部」という雑誌を探しているのですが……と尋ねたところ、店員さんは丁寧に在庫があるかどうか確認してくれましたが、その結果はやはり「うちでは取り扱っていません」でした。またもや無惨です。玉砕です。紀○○屋書店で扱っていないのなら、取り寄せをお願いするより他に手段はありません。
「この雑誌の取り寄せをお願いしたいのですが……」と切り抜いた新聞広告を見せると、店員さんは首を傾げています。どうしたのでしょうか。「これって、直販しかしてない本ですか?」「いや、新聞に掲載されていたので、書店でも扱っているものではないかと思うのですが……」無惨です。やはり「音楽倶楽部」の一般書店での認知度は限りなく透明に近いブルー、いや0%に近いようです(笑)。店員さんもこの雑誌の存在を知らないようでした。とにかく、取り寄せができるのかどうかを聞いてもらうことにして、この日は書店を後にしました。
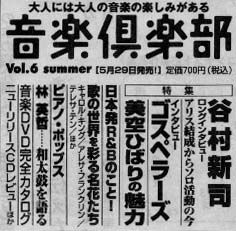 |
|
(写真)すべては、この新聞広告から始まった! |
|
|
|
(2)すれ違いの日々
とりあえず、書店から電話で連絡が入ることになっていました。注文できるのであれば、とうぜん取り寄せ注文するつもりでいました。しかし、注文してもらうには私が電話に出る必要があるのです。しかし、仕事もあり忙しい身。また、運悪く携帯電話も壊れていたため、電話による連絡はままならない状態。そのため、連絡は自宅の電話にしてもらうようになっていましたが、留守電のため非常に不安です。とうとう我慢できずに、木曜日こちらから書店へ電話をかけて取り寄せができているかどうか聞いてみました。
「先日『音楽倶楽部』の取り寄せをお願いしたのですが……」というと、「こちらにはまだ社員がきておりませんので、また折り返しお電話いたします」という返答。電話をする時間が少し早すぎたようです。でも、あと1時間以内には仕事に出ないといけません。後1時間以内に電話をしてほしい、と念を押して電話を切りました。電話を待っている間、宅急便の荷物が到着。受け取っていると、電話のベルが。あわてて電話口に出るも、ベルはすでに8回も鳴っていました。あやうくセーフ。電話の内容は、「まだ到着していません」とのこと。無惨です。でも、2〜3日後には届くだろうとのこと。それなら、週末にはゲットできるだろうと思い電話を切りました。
せっかちな私は、電話が来る前にまた書店へと足を運びました。それは日曜日の出来事。引換券を見せると、「連絡は?」と聞かれたので「いや、家にいないことが多いもので……」と言い訳がましく理由を述べた後で、探してもらいました。2〜3分後、返ってきた答えは「まだ到着してませんね〜」まったくもって無惨です。「本が入ったら、また連絡ください」と言い残して書店を立ち去った私ですが、顔が引きつっていたことは言うまでもありません(笑)。
|
|
|
(3)ようやくゲットだぜ!
あっというまに月曜日。仕事から疲れた帰ってきた私を待っていたのは、一本の留守電でした。「本が入荷しましたので……」私は次の日、朝一番で書店に乗り込んだのは言うまでもありません。
ようやくゲットだぁぁぁ!!! 早速読んでしまおうかと思ったのですが、これから仕事に行かなくてはなりません。ページをめくるのは、帰宅してからとなりました(涙)。
帰宅してからは、舐めるように読み始めました。まずは最初のページから。ゴスペラーズ特集です。ですが……どうでもいいです(笑)。目指すはその次、そう、チンペイさん特集です。なんと、タイトルは「過激なダンディズムのいま、そしてアリスの復活。」 すばらしいではありませんか。そういえば、憲法学入門の不思議の国のアリスのサブタイトルって、「帰れ、ダンディズムの都へ」でしたよね(笑)?
そして、次のリード文へ。「マイルドな笑顔を絶やさないけど、その活動には妥協がない。彼を見ているとナチュラルな過激派と呼びたくなってくる。自らの信念を貫きながら、存在感あふれる音楽を届け続けるシンガー・ソングライター、谷村新司に、いま、そしてアリスの復活を聞く。」 ワクワクするようなリード文ではありませんか。そして急いで次のページへ。
このインタビューはパート1とパート2に分けられています。パート1ではチンペイさんの活動、そしてパート2ではアリスの復活についての内容。従って、パート1のタイトルは「収穫(ハーヴェスト)、そして次のステージへ。」となっています。ここでちょっと気になったのは、シングル「ハーヴェスト」の画像がちょっとぼやけて荒くなっていたこと。おそらく、表紙で使った小さめのジャケットを拡大したのでしょう。せっかくのジャケットが台無しです。インタビュアーは前田祥丈さん、そして写真は寺崎道児さんです。そして私は、インタビューの文章へ目を移すのでした。
|
|
|
(4)パート1のインタビューを読んで(1)
まずは、最新シングル「ハーベスト」の話題。今までの人生を肯定しながらも、もう一歩前に、というメッセージが「昴」と同じではないか、というインタビュアー、前田祥丈さんの質問。チンペイさんは、「否定というものは一切ない」と前向きな姿勢。そして、メッセージもありつつ情に訴えるという二つの側面の理由は血液型が「AB型」だから(笑)。水も逃さぬ論理です(笑)。
ある音楽スタイルでヒットが出ると、周りはその形でしか評価をしなくなりますが、そのイメージをあえて壊す作戦にでるチンペイさん。ちょっぴり井上陽水さんにも共通している部分があるような気がしました。というのも、筑紫○也さんは陽水さんの大ファンで、ある時「陽水さんって、あまのじゃくですよね?」と質問をすると「そういわれると、『そうじゃない』って言いたくなりますよね(笑)」と言っていたのを思い出しました。
「ジャンルっていうのはレコード店の都合だけだろうと、僕らは思っていて。だから自分では、なんとかのジャンルですって言ったことは一回もないです。それは周りが決めるもんで、やっている方はただミュージックです。」
思い起こせば、History2000のツアーでチンペイさんは「ぼくらはフォークをやっていたのにニューミュージックと呼ばれた」と言っていました。矛盾しているような気がするのですが、どうなっているんでしょうか? ……悩んでいた私は、このインタビューを読み進むにつれてその悩みが解消されていくことに気がつきました。(続く)
|
|
|
(5)パート1のインタビューを読んで(2)
チンペイさんの「ぼくらはフォークをやっていたのにニューミュージックと呼ばれた」発言の矛盾について、私は読み進むに連れて意味がわかってきました。
インタビュアーは、シンガーとソングライターの両立について話を進めてきました。すると、その関係がうまくいかないのはソングライターの要求にシンガーが応えられないのが一番の原因、とチンペイさん。まさに悟りの境地ですね。ここに到達したのは、アルバム「海猫」を出されたときでした。でも、みんなは「えー、どうしちゃったんだろうね」って言ってましたよ(笑)とのチンペイさんの答えに、インタビュアーはひとこと、「このアルバムは凄いと思いました」(どう凄いんだ?)(笑)。
つまり、この当時はフォークというレッテルで聴かれていたから歌謡曲やジャズ、シャンソンなんかの匂いを出すとおかしいと思われる。ここからが大事なので、チンペイさんの言葉をそのまま引用してみます。
「でも、フォークというジャンルが廃れた時点で、はっきり見えてくるだろうなって(笑)。途中からニューミュージックと呼ばれましたけど、ニューはオールドになる。流行るっていうことは、廃れるっていうことだから、いつもスタンダードであればいいなと思ってました。」
さすがです。アリスは最初、フォークというレッテルを貼られ、それから音楽の流行がニューミュージックへ移行していったときにはニューミュージックと呼ばれた。しかし、チンペイさんはそんなことよりも、いつもスタンダードであればいい、という主張をしたかったのです! いやあ、長年の疑問が解消されました。氷山の氷が溶ける思いです(笑)。(続く)
|
|
|
Home |